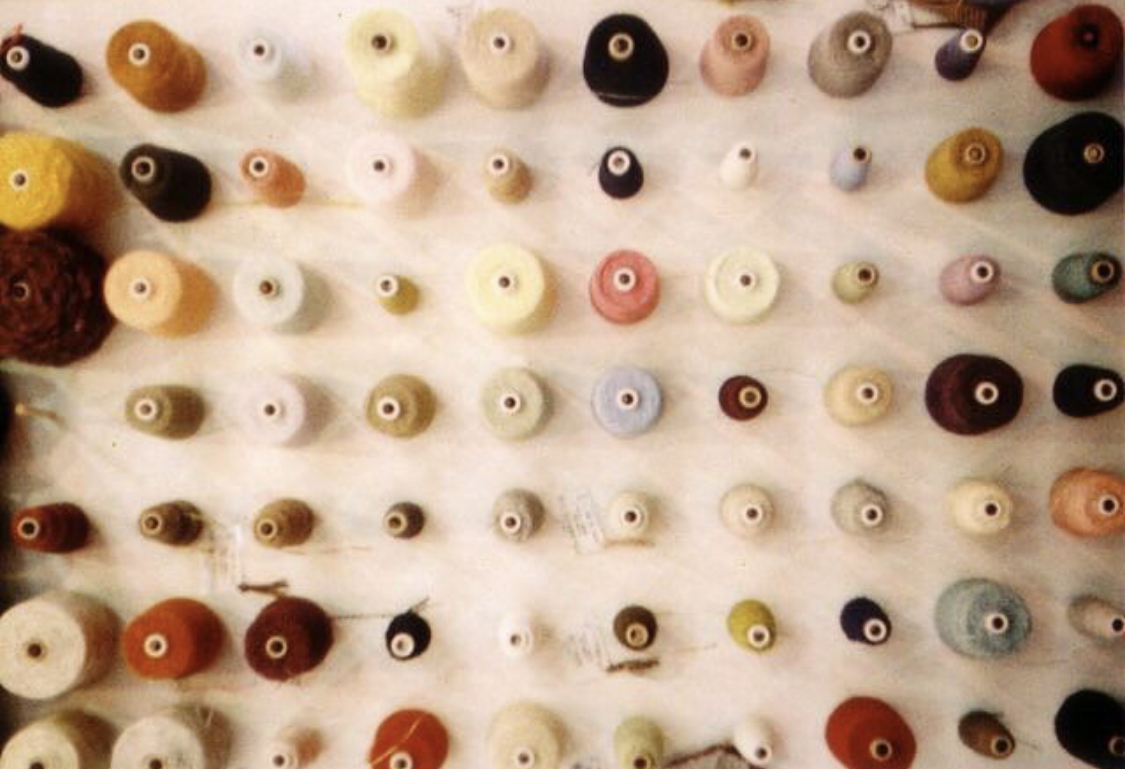日本の家をつくる
日本の家をつくる
サン工房の家の基本的なコンセプトですが、
「日本の家」=「和風の家」とは違います。
多くの方が抱く「和風の家」のイメージは、
瓦屋根で、二間続きの座敷があり、縁側があり、床の間があり、仏間があり、神棚があり、立派な設えが施された玄関があり、LDKや水廻り、寝室などの家族のスペースは北側の暗く寒い場所にあるそんな感じではないでしょうか。
サン工房はそういった「和風の家」のイメージをそのままトレースした家をつくりたいわけではありません。
確かに瓦屋根や格子などの和の設えや、地元天竜を中心に国産の木材は使用していますし、和っぽいね、和風だねという印象を持たれることも多いですが、それは「和風の家」をつくるために採用しているわけではありません。

「日本の家」とは、日本の気候風土(具体的には家を建てる場所の環境)において日本の生活文化の価値観を持った方が暮らしやすい家という意味で、「和風の家」と共通する部分もありますが、「和風の家」に加えより時代の変化を反映した家になっています。
家は時代に応じて様々な要素で変化します。
それは住む方が時代の変化に合わせてより暮らしやすい場所を造りたいという想いがある限り絶えず変わり続けます。
家を変化させる主な要素は、次のものが挙げられます。
・素材や技術の進化(土木技術、建築技術、空調機器、住設、窓、内外装材、断熱材、地震に耐える装置など)
・気候の変化や災害対応(温暖化、地震、水害、台風、花粉症、新型ウイルスなど)
・暮らしや家族の変化(省エネ、少子化、高齢化、IT化、テレワークなど)
サン工房の家の基本コンセプトの「日本の家」とは、これらの変化に対応した家という意味を持つため、いわゆる「和風の家」とは少し違って見えているのだと思います。

その理由から、サン工房の家が(和っぽい)とか、(和風だね)と見られるのは、サン工房の家が建つ場所の気候が昔も今も大きく変わらないので(四季があり、梅雨があり、夏は高温で雨が多く、冬は乾燥して風が強い)、その気候に対応する家も大きく変らないため、和っぽさが出ているのだと思います。
その時代、その場所、その家族にとって、丈夫で長持ちして、暮らしやすい家をつくる。
そのために、伝統や流行にとらわれず、必要な部分は残し、変えた方が良い部分は変える。
それがサン工房の目指す「日本の家をつくる」という基本コンセプトの考え方です。
これからも「日本の家」をつくり続けていきたいと思います。

設計・大西等